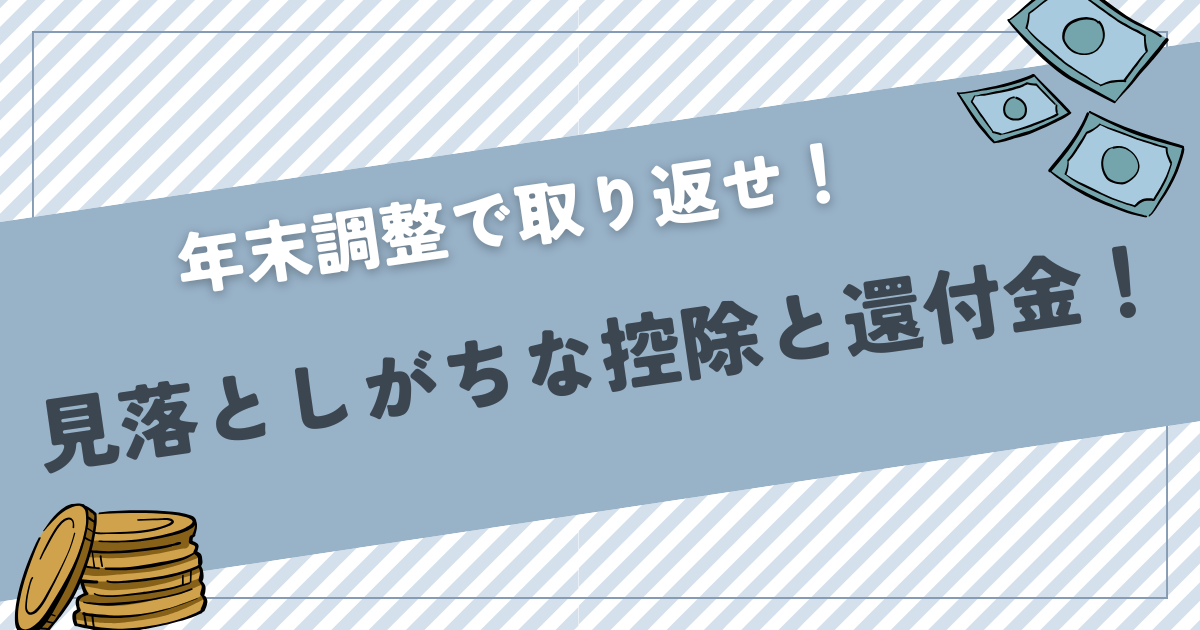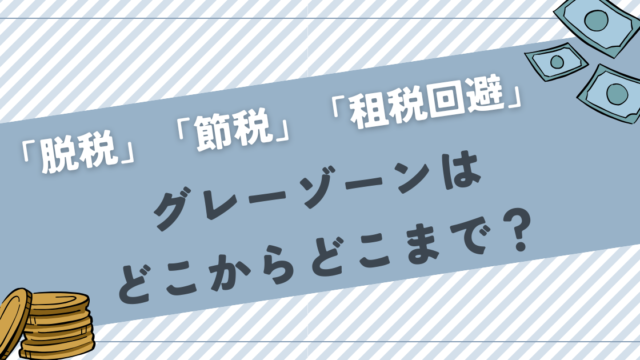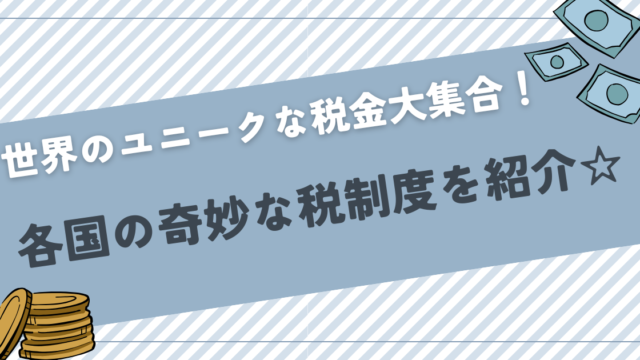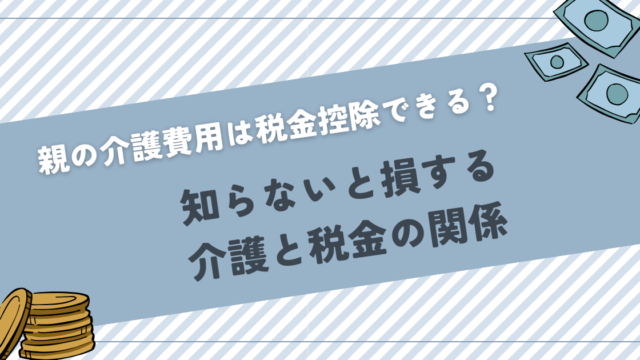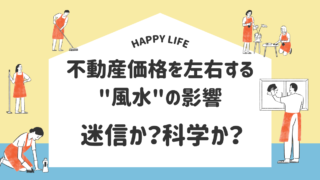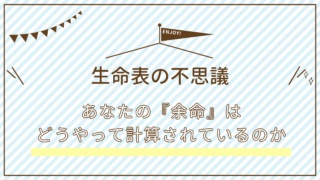みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
毎年11月から12月にかけて職場で行われる「年末調整」。
実はこの手続き、正しく行うことで平均2〜5万円、なかには10万円以上の還付金を受け取れるチャンスなのです!
国税庁の統計によると、年末調整で控除漏れが発生している人は全体の約22%にも上ります。
つまり、5人に1人以上が本来受け取れるはずのお金を取り損ねている計算です。
「難しそう」「面倒くさい」と思われがちな年末調整ですが、知っておくべきポイントはそれほど多くありません♪
今回は、初めて年末調整をする方でも分かるよう、基本から応用まで、特に見落としがちな控除と還付金についてわかりやすくまとめてみました!
年末調整の基本と仕組み

そもそも年末調整って何?
年末調整とは、1年間に納めすぎた所得税を精算する手続きです。
会社員の場合、毎月の給料から「源泉徴収」という形で所得税が天引きされていますが、これは概算で計算されています。
そのため、年末に正確な税金を計算し直し、納めすぎていた分は「還付金」として戻ってくるのです。
年末調整と確定申告の違い
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 対象者 | 会社員(主に) | 自営業者、副業がある人など |
| 手続き時期 | 11月~12月 | 2月16日~3月15日 |
| 手続き場所 | 勤務先 | 税務署またはe-Tax |
| 複雑さ | 比較的簡単 | やや複雑 |
年末調整は勤務先が代行してくれるので、必要書類を提出するだけで完了します。
一方、確定申告は自分で計算して申告する必要があります。
年末調整のスケジュール
- 10月下旬~11月:会社から年末調整の案内と必要書類が配布される
- 11月中旬~下旬:控除証明書が保険会社などから届く
- 11月末~12月中旬:必要書類を会社に提出
- 12月~翌年1月:還付金が給料に上乗せされる
よく知られた控除と申請方法
生命保険料控除
生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合に適用される控除です。
控除限度額:
- 生命保険料:最大4万円
- 介護医療保険料:最大4万円
- 個人年金保険料:最大4万円
- 合計で最大12万円
例えば、年間で生命保険料を5万円、介護医療保険料を3万円支払っている場合、合計7万円の控除が受けられます。所得税率20%の方なら、約1.4万円の還付金になります。
必要書類:保険会社から送られてくる「控除証明書」
住宅ローン控除
住宅ローンを組んで家を購入した場合、最大13年間(新築の場合)にわたり、ローン残高の1%が所得税から控除されます。
控除限度額:年間最大40万円(物件や契約条件により異なる)
例えば、3,000万円の住宅ローンを組んだ場合、年間30万円の控除が受けられる可能性があります。
必要書類:「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と添付書類
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の年間所得が一定額以下の場合に適用される控除です。
控除限度額:
- 配偶者控除:最大38万円(配偶者の年間所得が48万円以下)
- 配偶者特別控除:最大38万円(配偶者の年間所得が48万円超133万円以下)
例えば、あなたの年収が700万円で、配偶者の年収が103万円(所得38万円)の場合、38万円の配偶者特別控除が受けられます。
所得税率20%なら、約7.6万円の還付効果があります。
必要書類:「給与所得者の配偶者控除等申告書」
見落としがちな控除項目

小規模企業共済等掛金控除
iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済の掛金は、全額所得控除の対象となります。
控除限度額:支払った掛金の全額
例えば、iDeCoに月2.3万円(年間27.6万円)拠出している場合、27.6万円の所得控除が受けられます。所得税率20%なら、約5.5万円の還付効果があります。
必要書類:「小規模企業共済等掛金払込証明書」
医療費控除
年間の医療費が10万円を超えた場合(または所得の5%を超えた場合)に適用される控除です。
控除限度額:(支払った医療費 – 10万円)の金額(最大200万円)
医療費控除は年末調整ではなく確定申告で行うのが一般的ですが、「セルフメディケーション税制」は年末調整でも申請できることがあります。
必要書類:医療費の領収書または明細書
ふるさと納税(寄附金控除)
ふるさと納税は、実質2,000円の自己負担で各地の特産品がもらえる人気の制度です。
控除限度額:年収に応じて計算(目安として年収の約2%程度)
例えば、年収500万円の方なら、年間約10万円までふるさと納税が可能で、実質2,000円の負担で約9.8万円分の控除が受けられます。
必要書類:「寄附金控除に関する申告書」と寄附金受領証明書
控除を最大化するための準備
控除証明書の管理術
控除証明書は11月頃に各保険会社などから送られてきます。これらを紛失すると控除を受けられなくなるため、以下の管理方法がおすすめです!
- 専用のファイルを用意して、届いたらすぐに保管
- スマホで写真を撮っておく(バックアップ)
- 保険会社のアプリやWebサイトでデジタル証明書を取得
医療費の効率的な管理方法
医療費控除を受けるには1年分の領収書が必要です。効率的に管理するには…
- 医療費専用の封筒やファイルを用意する
- レシート保管アプリを活用する(国税庁公認のアプリも存在)
- クレジットカード明細で支払い記録を残す
年末までにやっておくべきこと
控除を最大化するために、年末までに検討すべきことがあります!
- 生命保険料の前払い:12月中に翌年分を前払いすれば、今年の控除対象に
- ふるさと納税の実施:12月中に手続きを完了させる(特に人気返礼品は早め)
- iDeCoの増額:余裕があれば12月分の掛金を増額
- 医療費控除対象の確認:メガネや治療費など、年内に支払いを済ませる
よくある年末調整の失敗と対処法

控除漏れの主な原因
控除漏れが発生する主な原因は以下の通りです!
- 控除証明書の紛失(約32%)
- 控除対象であることを知らなかった(約27%)
- 申告書の記入ミス(約18%)
- 提出期限を過ぎた(約13%)
- その他(約10%)
書類の記入ミスを防ぐポイント
- 記入例をよく確認する
- マイナンバーは正確に書く
- 金額の桁を間違えない(特に円と万円の混同)
- 押印が必要な書類は忘れずに押す
控除証明書を紛失したら?
控除証明書を紛失した場合は、すぐに発行元に再発行を依頼しましょう。
多くの保険会社では、Webサイトやアプリから再発行依頼が可能です。
再発行には1週間程度かかることがあるため、早めに対応することが重要です。
年末調整に間に合わなかったら?
年末調整の提出期限に間に合わなかった場合は、確定申告で対応することができます。
確定申告は翌年2月16日から3月15日までなので、その間に手続きを行いましょう。
年末調整以外の還付金チャンス
源泉徴収の還付金
年の途中で退職した場合や、収入が大きく減った場合は、源泉徴収で納めすぎた税金が発生していることがあります。
例えば、月給30万円(年収360万円想定)で源泉徴収されていたが、10月に退職して年収が300万円になった場合、約3万円の還付金が発生する可能性があります。
住民税の調整方法
住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、収入が大きく減った場合は「住民税の減免申請」を検討しましょう。
例えば、前年の年収が600万円だったが、今年は病気で働けず年収200万円になった場合、住民税の減免が受けられる可能性があります。
過去の控除漏れの救済方法
控除漏れに気づいた場合、過去5年間まで遡って還付を受けることができます。
「更正の請求」という手続きを税務署で行います。
例えば、3年前の医療費控除(還付額5万円)を申告していなかったことに気づいた場合、今からでも申請可能です。
家族全体の税金最適化

夫婦間での控除の分担戦略
夫婦の収入バランスによって、控除の受け方を工夫できます。
例えば、夫の年収が800万円(所得税率23%)、妻の年収が300万円(所得税率10%)の場合、医療費控除は税率の高い夫が申告した方が還付額が大きくなります。
扶養家族の確認と最適化
子どもや親が扶養に入る条件を確認し、最適な申告方法を選びましょう。
例えば、大学生の子どもがアルバイトで年間103万円以上稼ぐ場合、扶養から外れますが、「勤労学生控除」を利用することで税負担を軽減できることがあります。
デジタル時代の年末調整活用法
マイナポータルとの連携
マイナンバーカードとマイナポータルを活用すると、保険料控除証明書などの情報を電子的に一括取得できます。
2024年からは多くの企業でマイナポータル連携の年末調整が可能になり、紙の書類提出が不要になるケースが増えています。
実際に利用している人の約87%が「手続きが簡単になった」と回答しています。
スマホアプリを使った領収書管理
医療費の領収書管理には、スマホアプリが便利です。
国税庁が公認する「医療費控除の明細書作成アプリ」を使えば、レシートを撮影するだけで自動的に分類・集計してくれます。
まとめ

初めて年末調整をする方でも分かるよう、基本から応用まで、特に見落としがちな控除と還付金についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
年末調整は面倒な手続きではなく、あなたのお金を取り戻すチャンスです。
国税庁の調査によると、正しく控除を申請することで、平均して以下の還付金が期待できます(*’▽’)
- 生命保険料控除:約0.4~1.5万円
- 配偶者控除:約3~8万円
- 住宅ローン控除:約10~30万円
- iDeCo等の控除:約2~6万円
- ふるさと納税:約1~5万円
これらを組み合わせると、年間で10万円以上の税金が戻ってくる可能性も十分にあるのです。
税金は正しく納め、戻るべきものはしっかり取り戻す。それが賢いお金の管理の第一歩です。
この記事を参考に、ぜひ今年の年末調整を見直してみてください!