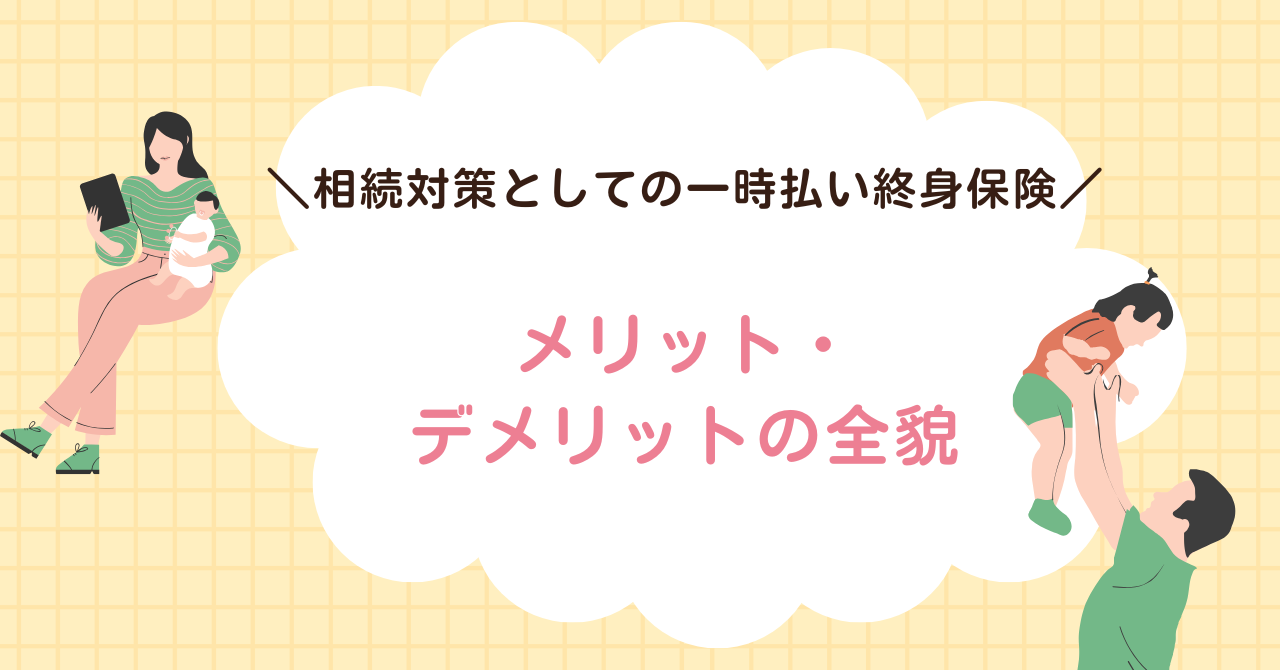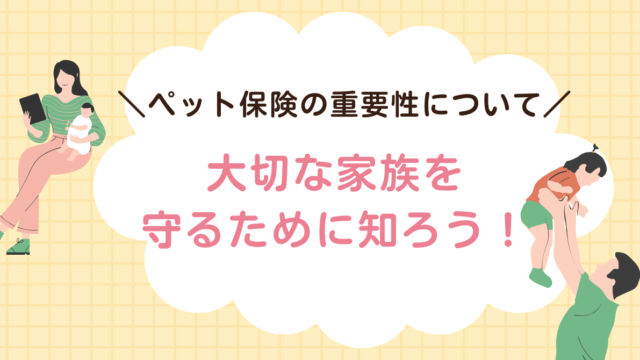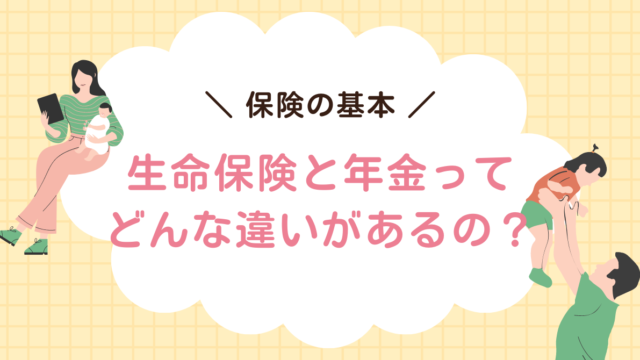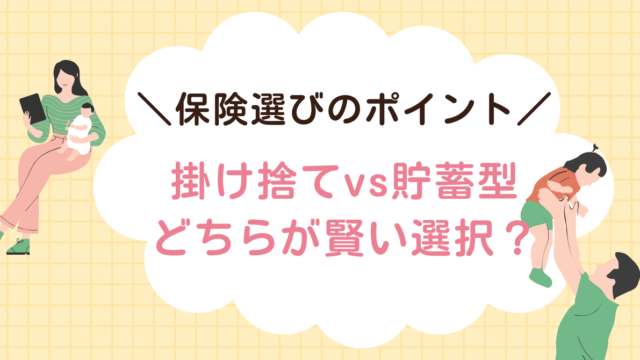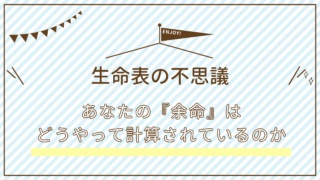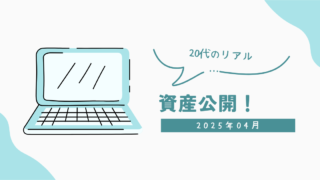みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
相続対策は、資産をお持ちの方にとって避けて通れない重要課題ですよね。
特に日本では、相続税の基礎控除額が2015年に「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられて以降、相続税の対象となる方が増加しています!
国税庁の統計によれば、相続税の申告件数は改正前の約4万件から、現在は年間約11万件と大幅に増加しているそうです。
このような状況の中、一時払い終身保険は相続対策の有力な選択肢として注目を集めています。
しかし、「本当に効果的なのか」「どのような場合に向いているのか」といった疑問をお持ちの方も多いかもしれません。
今回は、相続対策としての一時払い終身保険のメリット・デメリットを、具体的な数字や事例を交えながらわかりやすくまとめてみました!
一時払い終身保険の基本理解

一時払い終身保険とは
一時払い終身保険とは、保険料を一括で支払い、死亡時に保険金が支払われる生命保険商品です。
通常の終身保険が毎月・毎年の保険料支払いを前提としているのに対し、一時払いは「まとまった資金を一度に支払う」という特徴があります!
主な商品タイプ
一時払い終身保険には、主に以下の3つのタイプがあるので、興味ある方は覚えておくとよいでしょう。
また、すでに保険で一時払いの商品を持っている方は、ご自身がどのようなものをもっているか確認しておくとよいかもしれませんね。
- 円建て型:日本円で支払い、日本円で受け取る最もシンプルなタイプ。安定性が高い。
- 外貨建て型:外貨(米ドル・豪ドルなど)で運用される商品。為替リスクがある一方、円建てより利回りが高い場合が多い。
- 変額型:投資信託などで運用され、運用成績により保険金額が変動する商品。
一時払い終身保険の代表的な保険会社の平均解約返戻率は以下の通りです!
| 契約からの経過年数 | 円建て型 | 外貨建て型(米ドル) |
|---|---|---|
| 1年 | 約93% | 約90% |
| 5年 | 約96% | 約98% |
| 10年 | 約100% | 約105% |
| 15年以降 | 約102% | 約110%〜 |
※これらの数値は2024年現在の平均的な商品を想定したものです。実際の商品は会社や条件によって異なります。
相続対策としての一時払い終身保険のメリット
死亡保険金の非課税枠の活用
生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、1,500万円(500万円×3人)が非課税となります。
相続税の納税資金対策
相続税の納税期限は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内です。
不動産などの換金が難しい資産が多い場合、納税資金の確保が課題となりますが、生命保険金は比較的迅速に受け取れるため、納税資金対策として有効といわれています!!
生前贈与との組み合わせ効果
年間110万円の贈与税非課税枠を活用し、子や孫に毎年資金贈与して一時払い終身保険に加入してもらう方法も効果的です。
例えば、70歳の親から50歳の子への10年間の贈与(計1,100万円)を原資に一時払い終身保険に加入した場合、将来の死亡保険金は約1,200万円〜1,300万円程度になる可能性があります。
遺産分割対策としての活用法
不動産などの分割が難しい資産と保険金を組み合わせることで、円滑な遺産分割が可能になります。
例えば、長男に自宅不動産(5,000万円)を相続させ、次男には一時払い終身保険の死亡保険金(5,000万円)を受け取らせるといった方法が考えられます。
相続対策としての一時払い終身保険のデメリット

高額な保険料と流動性の低下
一時払い終身保険はまとまった資金(一般的には300万円〜)が必要です。
また、契約後すぐに解約すると元本割れするリスクがあります。
特に契約から1〜2年以内の解約返戻率は90%程度のことが多く、1,000万円の保険料に対して900万円程度しか戻ってこない可能性もあるので気をつけましょう!
外貨建て商品のリスク
外貨建て商品は、為替変動リスクがあります。
例えば、1ドル=100円の時に10万ドル(1,000万円)の保険に加入し、受取時に1ドル=80円になった場合、円換算で800万円となり、200万円の為替差損が生じます。
また、為替手数料(TTSとTTBの差、一般的に1〜3円程度)も考慮する必要があります。
自分一人でこのあたりを把握するのは大変なので、担当者と連絡を取って、タイミングを考えるとよいかもしれませんね!
低金利環境下での利回りの低さ
日本の低金利環境下では、円建て型の一時払い終身保険の利回りは年0.5%前後のものが多く、インフレ率(直近の日本のインフレ率は約2%程度)を下回る場合があります。
相続税法改正リスク
相続税制度は変更される可能性があります。
例えば、過去には相続税の基礎控除額の引き下げや、生命保険の非課税枠の縮小が議論されたことがあります。
将来的な制度変更によって、現在期待できる効果が得られなくなるリスクがあるので注意しましょう。
一時払い終身保険が特に向いているケース
相続対策をすべき資産規模の目安
一般的に、預貯金や不動産などの純資産額が「基礎控除額+2,000万円」を超える場合に、一時払い終身保険の検討価値があります。
例えば、夫婦と子供2人の場合、基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)なので、総資産が6,200万円を超える場合は検討対象となります。
高齢者やすでに相続が近い方への提案
特に75歳以上の高齢者では、一時払い終身保険の相続税評価減効果(20%)が大きく、効果的な場合があります。
例えば、80歳の方が1億円の保険に加入した場合、解約返戻金は契約直後でも約98%(9,800万円)となり、相続税評価額は7,840万円となります。
分散投資としての検討
相続対策だけでなく、資産分散の観点からも一時払い終身保険は有効です。
預貯金、不動産、有価証券などと組み合わせることで、リスク分散になります。
一時払い終身保険の選び方と注意点

商品選びのポイント
- 保険会社の財務健全性:ソルベンシー・マージン比率(200%以上が健全とされる)は重要な指標です。大手生保では800%〜1,000%程度の会社が多いです。
- 解約返戻率の推移:契約から5年、10年、15年後の解約返戻率を確認しましょう。
- 契約者配当金の有無:配当金がある商品は、将来的に上乗せ効果が期待できます。
契約時の確認事項
- 契約者と被保険者の関係:通常、契約者=保険料負担者、被保険者=保険の対象となる人、受取人=保険金を受け取る人の関係を明確にします。
- 保険料の資金源:贈与税対策と組み合わせる場合、贈与の記録を残しておくことが重要です。
事例紹介
実際の活用事例(匿名化した成功例)
事例1:不動産を所有する70代夫婦のケース
- 資産状況:自宅(5,000万円)、賃貸アパート(1億円)、預貯金(3,000万円)
- 相続人:子供2人
- 対策:預貯金2,000万円で一時払い終身保険(外貨建て)に加入
- 効果:相続税評価額が400万円減少、死亡保険金の非課税枠(1,000万円)を活用、納税資金も確保
事例2:事業承継を控えた経営者のケース
- 資産状況:自社株式(2億円)、自宅(7,000万円)、預貯金(1億円)
- 相続人:事業承継予定の長男、その他子供1人
- 対策:預貯金5,000万円で一時払い終身保険に加入、受取人を事業を承継しない次男に指定
- 効果:自社株式は長男が相続、次男は保険金で実質的に平等な相続を実現
注意すべき失敗例
失敗例:流動性を考慮しなかったケース
- 資産状況:預貯金(8,000万円)、不動産(2,000万円)
- 対策:預貯金7,000万円で一時払い終身保険に加入
- 問題点:生活資金が不足し、契約から2年後に解約。解約返戻率は約94%で、420万円の損失が発生
まとめ

相続対策としての一時払い終身保険のメリット・デメリットを、具体的な数字や事例を交えながらまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
一時払い終身保険は、相続対策として一定の効果が期待できますが、万能ではありません。
具体的には以下のポイントを押さえておくことが重要でしょう(*’▽’)
- 非課税枠の活用と評価減効果は魅力的だが、過度に期待しないこと
- 資産全体のバランスを考慮し、流動性を確保すること
- 自分の相続状況に合わせて商品を選択すること
- 制度改正リスクを認識しておくこと
相続対策にはさまざまな方法があり、一時払い終身保険はその一つの選択肢に過ぎません。
資産状況、家族構成、将来の希望など、トータルな視点で相続計画を立てることが大切です。
専門家(FP・税理士など)に相談しながら、自分に合った相続対策を進めていくことをおすすめします♪