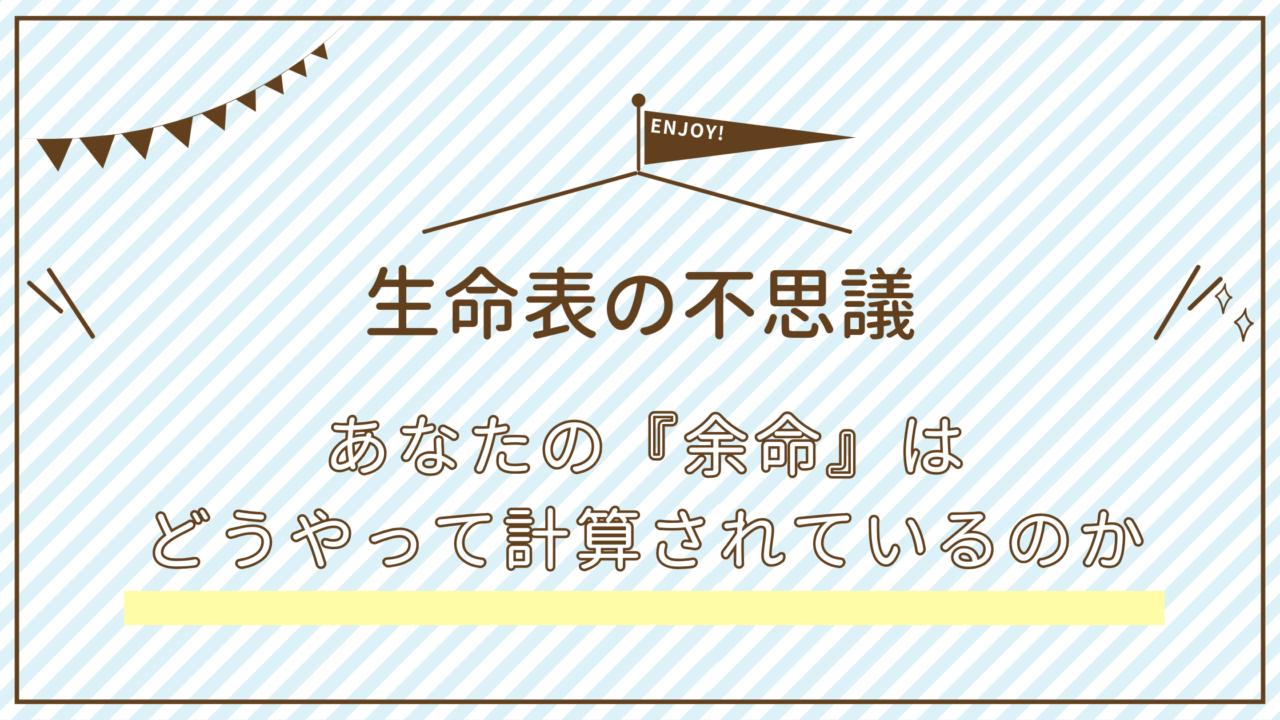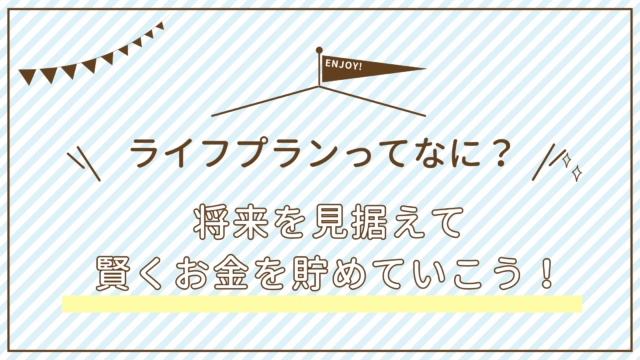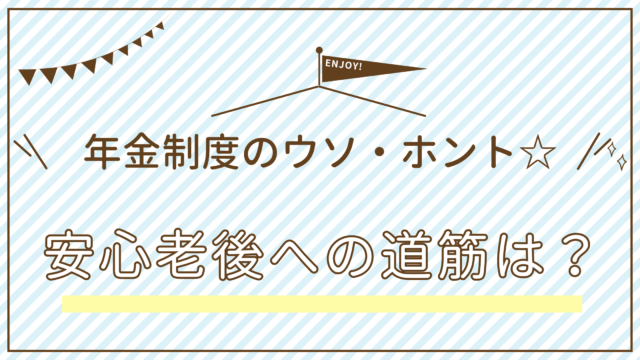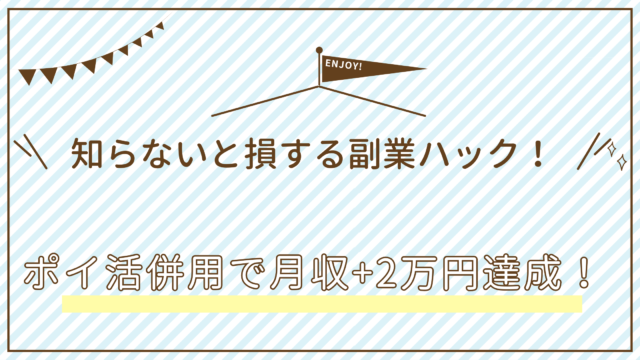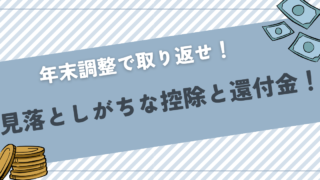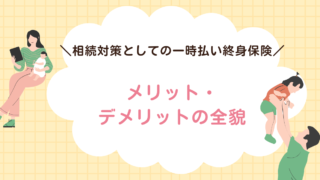みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
「平均余命は80歳を超えました」「日本人女性の平均寿命は世界トップクラス」というニュースを耳にすることがあります。
しかし、この「余命」や「平均寿命」という言葉が実際には何を意味しているのか、どのようにして計算されているのかをご存知でしょうか?
実は「余命」は単なる運命的な数字ではなく、緻密な統計手法によって算出された確率的な指標です。
この数字は私たちのライフプラン、特に老後の資金計画において非常に重要な役割を果たします。
今回は、ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から、生命表の仕組みと平均余命の計算方法についてわかりやすくまとめてみました♪
生命表の基本

生命表とは
生命表とは、ある時点における各年齢の死亡率をもとに、各年齢での平均余命や生存率などを表したものです。
日本では厚生労働省が定期的に作成・公表しており、「完全生命表」と「簡易生命表」の2種類があります。
完全生命表は5年ごとに国勢調査の結果に基づいて作成される詳細なデータで、簡易生命表は毎年の人口動態統計に基づいて作成されるより簡略化されたデータです。
どちらも死亡率や平均余命を知るための基礎資料として重要です。
生命表から読み取れる情報
生命表からは以下のような情報が読み取れます!
- 年齢別死亡率:各年齢での死亡確率
- 生存数:ある年齢まで生存する人数(通常10万人を基準とする)
- 定常人口:特定の年齢層の人口構成
- 平均余命:特定の年齢における平均的な残りの生存年数
生命表の実データ
以下は、2020年の日本の簡易生命表から抜粋した主要な年齢における平均余命のデータです!
| 年齢 | 男性の平均余命(年) | 女性の平均余命(年) |
|---|---|---|
| 0歳 | 81.64 | 87.74 |
| 20歳 | 62.15 | 67.96 |
| 40歳 | 42.81 | 48.19 |
| 60歳 | 24.36 | 29.57 |
| 65歳 | 19.98 | 24.80 |
| 70歳 | 15.84 | 20.10 |
| 80歳 | 9.13 | 12.10 |
| 90歳 | 4.34 | 5.59 |
*出典:厚生労働省「2020年簡易生命表」
平均余命の計算方法
平均余命の定義
平均余命とは、ある年齢の人が平均してあと何年生きるかを示す統計的指標です。
重要なのは、これは過去のデータに基づいた推計値であり、医学の進歩や生活環境の変化によって変動するという点です。
計算式
平均余命の計算は次のように行われます!
- ある年齢xの人口集団を考える
- この集団の各年齢での死亡率を適用し、何人が何歳まで生存するかを算出
- 集団全体の残りの生存年数の総和を、x歳時点の生存者数で割る
数式で表すと…
平均余命(x歳) = x歳以降の生存年数の総和 ÷ x歳時点の生存者数
計算例
例えば、簡易的な計算例として、65歳の男性の平均余命を考えてみましょう!
- 65歳時点での生存者数を10万人とする
- 以降の各年齢での死亡率を適用すると、66歳までに1,500人が死亡、67歳までにさらに1,600人が死亡…という具合に減少していく
- 全員が死亡するまでの総生存年数(65歳以降の各年齢の生存者数の合計)が約200万人年だとすると
- 平均余命 = 200万人年 ÷ 10万人 = 20年
これは上記の表に示された65歳男性の平均余命19.98年にほぼ一致します。
生命表の応用分野

保険数理への応用
生命表は生命保険や年金保険の保険料計算の基礎となります。
保険会社は生命表を用いて、加入者が将来何歳まで生きる可能性があるかを推計し、適切な保険料を算出します。
【具体例】 50歳男性の終身保険(死亡保険金1,000万円)の保険料計算
- 平均余命:約32年
- 年間死亡率:約0.5%~(年齢とともに上昇)
- 保険会社は死亡率や運用利回りから保険料を約17,000円/月などと算出
年金制度設計への影響
公的年金制度も平均余命の延びを考慮して設計されています。
日本の年金制度では、平均余命の延びに対応するため、支給開始年齢の引き上げが行われてきました。
【データ】 日本の年金支給開始年齢の変遷
- 1954年:55歳から支給開始
- 1973年:60歳に引き上げ
- 2001年以降:段階的に65歳へ引き上げ
- 現在:さらなる引き上げが議論されている
これらの変更は、平均寿命の延びに対応するためのものです。
1950年代の日本人の平均寿命は男性約60歳、女性約63歳でしたが、現在は男性約81歳、女性約87歳まで延びています。
医療政策や公衆衛生への活用
生命表は、健康寿命の延伸や疾病予防の取り組みの効果を測定するためにも使われます。
【データ】 日本の健康寿命と平均寿命の差(2019年)
- 男性:平均寿命81.41歳、健康寿命72.68歳、差約8.7年
- 女性:平均寿命87.45歳、健康寿命75.38歳、差約12.1年
*出典:厚生労働省「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」
この差を縮めることが、医療政策や公衆衛生政策の重要な目標となっています。
余命の変動要因
時代による平均余命の変化
【データ】日本の平均寿命の変遷
- 1900年頃:男性約42歳、女性約44歳
- 1950年:男性約60歳、女性約63歳
- 1980年:男性約74歳、女性約79歳
- 2020年:男性約81歳、女性約87歳
*出典:厚生労働省「生命表」
この劇的な変化は、乳幼児死亡率の低下、感染症対策の進歩、生活環境の改善、医療技術の発展など様々な要因によってもたらされました。
主要国との比較
【データ】主要国の平均寿命(2020年)
- 日本:男性81.6歳、女性87.7歳
- アメリカ:男性76.3歳、女性81.2歳
- イギリス:男性79.4歳、女性83.1歳
- ドイツ:男性78.9歳、女性83.6歳
- フランス:男性79.2歳、女性85.3歳
*出典:OECD Health Statistics 2022
日本は女性の平均寿命が世界最高水準を維持しており、男性も高い水準にあります。
地域や社会経済的要因による違い
日本国内でも都道府県によって平均寿命に差があります。
【データ】都道府県別平均寿命上位・下位(2020年)
- 上位:男性(滋賀県82.7歳、京都府82.3歳)、女性(長野県87.7歳、滋賀県87.6歳)
- 下位:男性(青森県80.0歳、秋田県80.1歳)、女性(青森県86.0歳、大阪府86.5歳)
*出典:厚生労働省「都道府県別生命表」
この差は、食生活、生活習慣、医療アクセス、労働環境など様々な要因が影響していると考えられています。
FPとしての活用法

ライフプランニングにおける余命データの活用方法
FPとしてクライアントのライフプラン設計を行う際、平均余命は重要な参考指標となります。
しかし、単に平均値を使用するのではなく、クライアントの家族歴、健康状態、生活習慣などを考慮して個別に検討することが重要です。
【データ】長寿確率(65歳の人が特定の年齢まで生存する確率)
- 85歳まで生存する確率:男性約54%、女性約74%
- 90歳まで生存する確率:男性約30%、女性約52%
- 95歳まで生存する確率:男性約11%、女性約26%
- 100歳まで生存する確率:男性約2%、女性約7%
*出典:厚生労働省「2020年簡易生命表」より計算
このデータから、特に女性は半数以上が90歳まで生きる可能性があることがわかります。
老後資金計画への応用
【具体例】65歳女性の老後資金計画
- 平均余命:約25年(90歳まで)
- 長寿リスク考慮:30年(95歳まで)を想定
- 必要生活費:月20万円(年間240万円)
- 30年分の必要資金:7,200万円
- 年金収入:月13万円(年間156万円)
- 不足額:月7万円(年間84万円)
- 30年分の不足総額:2,520万円
このように、平均余命ではなく、より長い期間を想定した計画が必要です。
長寿リスクへの対応策
長寿リスクに対応するためには、以下のような対策が考えられます!
- 資産の長期運用戦略
- 【データ】インフレ率2%の場合、25年後の貨幣価値は約60%に低下
- 対策:分散投資、インフレヘッジ資産の活用
- 公的年金の繰下げ受給
- 【データ】70歳まで繰下げると、年金額が最大42%増加
- 例:65歳時点で月額15万円の年金が、70歳繰下げで月額21.3万円に
- 個人年金や終身保険の活用
- 終身年金:一生涯にわたって年金を受け取れる商品
- 例:65歳で3,000万円を原資に、月額約10万円の終身年金を受け取る
まとめ
ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から、生命表の仕組みと平均余命の計算方法についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
「余命」という言葉は時に重たく感じられますが、FPとしては客観的なデータとして冷静に扱うことが大切です。生命表から得られる平均余命のデータは、クライアントの将来設計を支える重要な指標の一つです。
しかし、それはあくまで統計的な平均値であり、個人の実際の寿命を予測するものではありません。上記のデータが示すように、65歳の方の約半数が90歳まで生きる可能性がある現代において、「長生きするリスク」に備えた余裕のある計画を立てることが重要です。