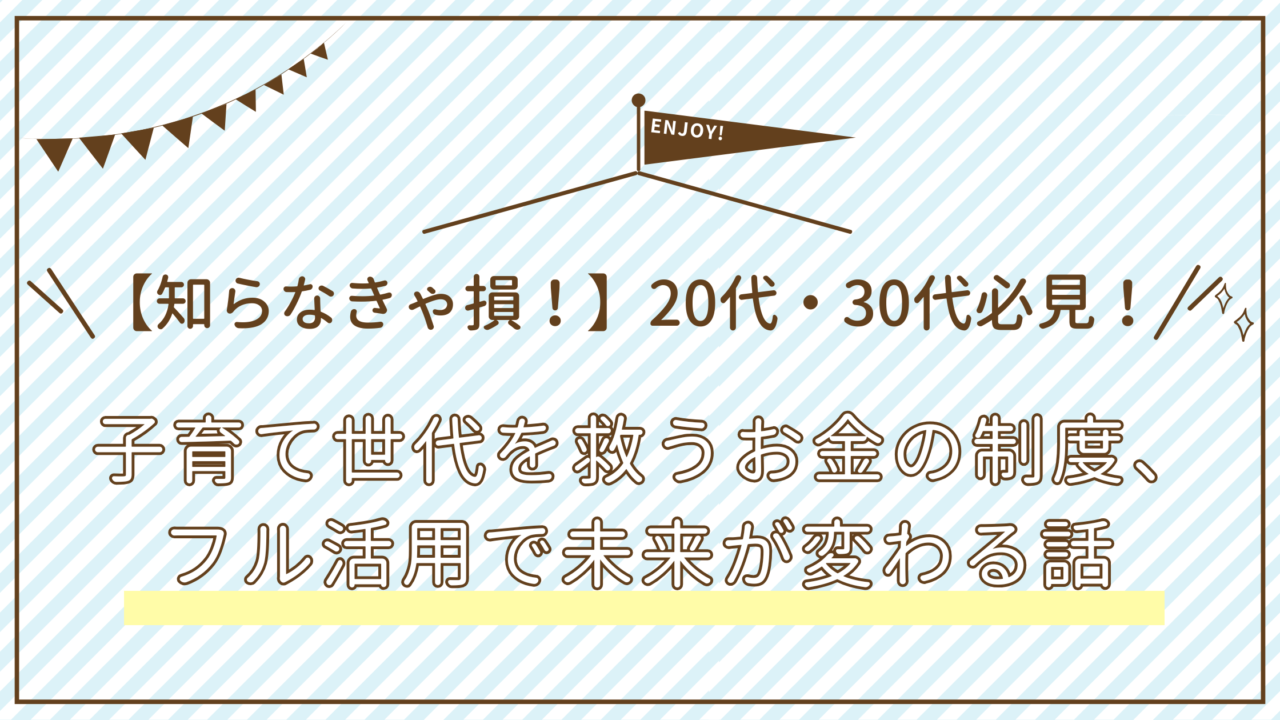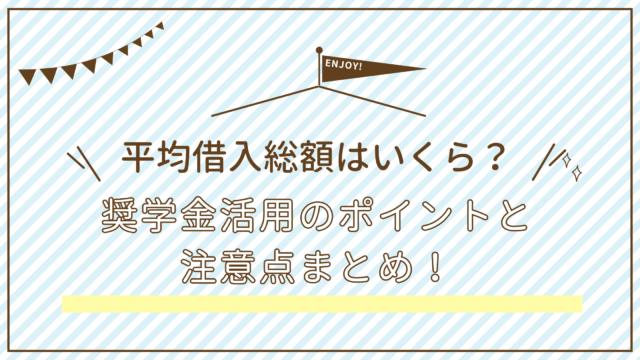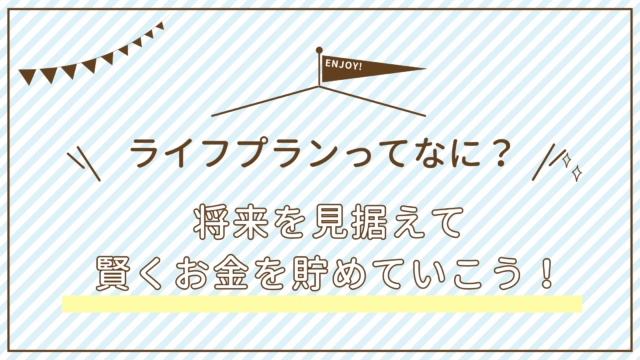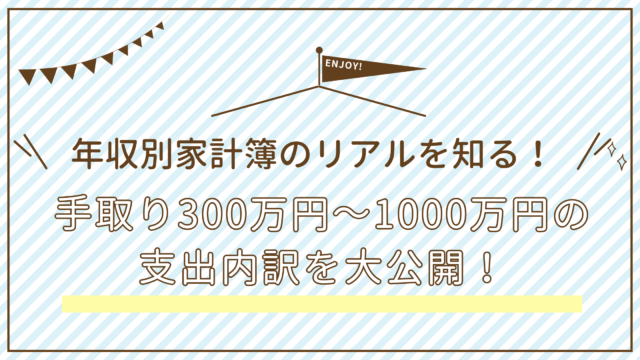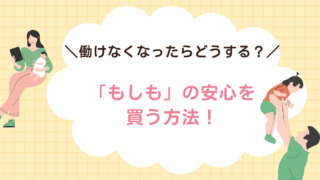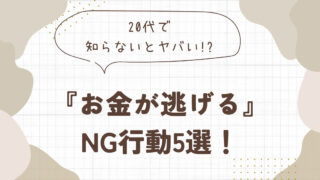みなさまこんにちは、いちまるです(*’▽’)
「結婚、出産、マイホーム…憧れるけど、ぶっちゃけお金ってめちゃくちゃかかるよね?」
20代後半から30代で、これからのライフイベントを考えたり、すでに子育て真っ最中だったりするあなた。お金の不安、すごくよくわかります!
FPとして、私も多くの若い世代から「不安で次の一歩を踏み出せない」という相談を受けます。
子育てには、ミルク代やおむつ代、習い事の月謝、将来の教育費と、心配のタネは尽きません。でも、実は国や自治体、会社や民間サービスには、そんな私たちの「お金の不安」を吹き飛ばしてくれる、とっておきの「お得な制度」が山ほどあるって知ってましたか?
今回は、「本当に使える」「これだけは押さえておくべき」な公的・民間の多様な支援制度をわかりやすくまとめてみました♪
国の制度はマストでチェック!みんなが使える「公的支援」の基本

日本全国どこでも受けられる、国の基本的な支援制度は、子育て家庭にとってのまさに「土台」です。
児童手当:子どもがもらえる!将来の貯金箱を育てよう
子育て世代なら聞いたことがある児童手当は、お子さんが中学校を卒業するまで、国が子どもの成長を応援するために支給してくれる手当です。
3歳未満なら月額1万5000円、3歳から小学校卒業までは月1万円(3人目以降は1万5000円)、中学生は全員月1万円がもらえます。
夫婦と子ども2人の世帯だと、世帯年収960万円くらいから減額され始め、1200万円を超えると支給されなくなる目安です(正確な数字は自治体でご確認ください)。
この手当は年に3回(6月、10月、2月)まとめて支給されます。
お子さんが生まれたり引っ越したりしたら、15日以内に申請しないと受け取れなくなるので、忘れずに手続きしましょう。
多くの家庭がこの児童手当を教育資金の準備に充てています。
例えば、0歳から中学校卒業までの15年間、毎月平均1万円を貯め続ければ、合計180万円にもなりますよ。
医療費助成:子どもが熱を出しても、お財布は安心!
子どもは急な発熱やケガが多いもの。。。
そんな時、家計を助けてくれるのが医療費助成制度です。
これは、小さなお子さんが医療機関を受診した際の自己負担分を、国や自治体が助成してくれる制度。
ただし、住んでいる場所によって内容が大きく異なります。
例えば、東京都の多くの区では18歳まで助成対象ですが、地域によっては就学前までだったり、自己負担金が必要だったりすることも。
お住まいの市区町村のホームページで「子ども医療費助成」の情報をチェックし、病院では健康保険証と一緒に「医療費助成の受給者証」を提示しましょう。
出産・育児に関する給付金:出産から育休まで、お金の心配を減らそう!
妊娠、出産、育児休業中に収入が減ったり、大きな出費があったりする際に、国や健康保険組合から支給される給付金があります。
- 出産育児一時金
健康保険加入者が出産した際に、1児につき50万円(産科医療補償制度加入の医療機関の場合)が支給されます。出産費用をカバーする大きな助けになりますし、直接病院に支払ってもらう制度を利用すれば、窓口での負担も減らせます。 - 出産手当金
会社の健康保険に加入している女性が産休中に受け取れる給付金で、産休中の生活を保障します。出産予定日の42日前から出産後56日までの期間が対象で、おおよそ「お給料の3分の2」が目安です。 - 育児休業給付金
雇用保険に加入していれば、育児休業中の収入をサポートしてくれる制度です。育休開始から最初の半年間は、休業に入る前のお給料の67%が支給され、それ以降は50%になります。厚生労働省の調査(令和4年度)でも男性の育児休業取得率が上昇しており、夫婦で育休を交代取得する「パパ・ママ育休プラス」も活用すれば、給付期間を延長して安心を確保できます。
地域限定!自治体ならではの「ローカルお得制度」を探せ!
国の制度に加えて、お住まいの市区町村が独自に提供している子育て支援制度もたくさんあります。これらは「地域の特性」によって内容が大きく異なるので、情報収集がカギです。
医療費助成の自治体アレンジ版:さらに手厚いサポートがあるかも!
多くの自治体が国の医療費助成をさらに拡充し、「高校生までの医療費を助成」したり、「所得制限なしで医療費を無償化」している地域も存在します。
お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで確認し、あなたの街の制度をチェックしてみてください。
各種助成金・補助金:こんなものまで!?意外な支援を見つけよう
出産から子育てまで、自治体独自の助成金や補助金は多岐にわたります。任意の予防接種費用補助、ベビーシッター利用補助、不妊治療費助成、紙おむつ・粉ミルクの現物支給など。
地域のお店で割引や特典が受けられる「子育て支援パスポート」も便利です。
例えば、東京都世田谷区では、多子世帯の保育料軽減や病児保育の利用補助など、きめ細やかな支援策を実施しています。これらの情報は、お住まいの市町村の「子育て支援課」や「福祉課」に問い合わせるのが確実でしょう。広報誌や子育てイベントでも新しい制度が紹介されることがありますよ。
普段使いでお得に!「民間サービス」で家計を賢く守るワザ

公的制度だけでなく、普段使っている民間サービスをちょっと賢く利用するだけで、子育て家庭の家計はもっとラクになります。これぞ、令和時代の節約術!
ふるさと納税:実質2,000円でオムツも食料もGET!
今や常識になりつつあるふるさと納税は、好きな自治体に寄付すると、寄付したお金のほとんど(2,000円だけ自己負担)が税金から控除され、お礼としてその自治体の特産品がもらえるお得な制度です。
子育て世代には、毎日消費するおむつや粉ミルク、お米や肉、野菜といった食費の負担を軽減できる返礼品が大人気です。おもちゃや体験チケットを選んで、教育・娯楽費の節約に充てることもできますよ。
「ふるさとチョイス」や「楽天ふるさと納税」でも子育て・ベビー用品カテゴリが人気。ご自身の年収や家族構成で控除上限額を確認し、確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」(寄付先が5自治体以内など条件あり)の利用も検討しましょう。
企業の福利厚生:まさかの「会社のお金」が子育てを助ける!?
意外と見落としがちなのが、あなたやパートナーの勤務先が提供している福利厚生制度です。
住宅手当や家賃補助で住居費の負担を減らしたり、育児支援制度として時短勤務やベビーシッター補助、企業内保育園などがあることも。給与天引きで無理なく貯蓄ができる財形貯蓄制度も、教育費の準備に役立ちます。
社員割引や提携施設割引も、日々の生活費やレジャー費の節約に繋がるので、就業規則や人事部に問い合わせてみてください。
ポイント活用&キャッシュレス決済:いつもの買い物をお得に変える錬金術
普段の買い物で、ちょっとした工夫をするだけで、地道に節約しつつポイントをザクザク貯めて、それを子育て費用に充てるという、まさに「錬金術」のようなワザです。
クレジットカードやスマホ決済、ポイントカードなどを賢く利用しましょう。
高還元率のカードを選んだり、スーパーやドラッグストアのポイントアップデーを狙ってまとめ買いしたり、各キャッシュレス決済アプリのキャンペーンをチェックして利用するのも効果的です。
総務省の家計調査(2023年)を見ると、食費や光熱費は二人以上の世帯の消費支出の大きな割合を占めます。これらの固定費をキャッシュレスで支払ってポイントを貯めるだけで、年間数万円単位のポイント獲得も夢じゃありません。貯まったポイントで子どものオモチャを買ったり、習い事の費用に充てたり…賢くポイントを貯めて、家計を助けていきましょう。
未来のために、今すぐ動こう!
ここまで、子育て世代のあなたが知っておくべき公的・民間の様々なお金制度について解説してきました。最後に、これらの制度を最大限に活用するためのFPからのアドバイスをお伝えしますね。
情報のアンテナは常に張り巡らせて!
子育て支援制度は、社会情勢や自治体の財政で頻繁に改正されたり、新たな制度が生まれたりします。
自治体の公式サイト、広報誌、SNSを定期的にチェックし、子育て支援センターや地域のイベントにも積極的に足を運んでみてください。
FPなどお金の専門家からの情報も有効です。
申請は「見つけたらすぐ」「モレなく」が鉄則!
多くの制度には、申請期間や必要な書類が定められています。
「使えるかも?」と思ったら、情報収集から始め、すぐに申請準備に取り掛かりましょう。
申請期限が迫っている場合もあるので、「早めのアクション」がカギです。必要な書類をきちんと揃え、「申請モレ」がないように注意してください。
分からないことがあれば、迷わず担当窓口に問い合わせましょう。せっかくの制度も、申請しなければゼロですから!
制度はあくまで「きっかけ」!全体のマネープランが未来を変える
今回ご紹介した制度は、子育て家庭の家計を助ける強力なツールです。
しかし、これらはあくまで一時的な支援や、特定目的の補助であることがほとんど。
子どもの成長に伴う教育費、住宅購入、老後資金など、将来を見据えた総合的なライフプランニングが不可欠です。
「いつ、どれくらいのお金が必要になるのか」「そのために今何ができるのか」を具体的に把握することで、漠然としたお金の不安が解消され、より計画的に子育てを楽しめるようになるでしょう。
もし「うちの場合はどうすればいいんだろう?」と感じたら、ぜひFPにご相談ください。
あなたの状況に合わせた最適なアドバイスで、子育て世帯の家計と未来をサポートしてもらえるでしょう(*’▽’)
まとめ

いかがでしたでしょうか?
子育て家庭を助ける公的・民間のお金制度は、意外と身近にたくさん存在し、一つ一つが、あなたの家計をグッと楽にしてくれる可能性を秘めています。これらの制度を賢く、そして積極的に活用することこそが、子育ての負担を減らし、もっと笑顔あふれる毎日を送るための秘訣なんです。
この記事が、あなたの未来を明るくする一助となれば、これほど嬉しいことはありません。ぜひ、今日から「お金の制度」を味方につけて、最高の「子育てライフ」を実現していきましょう!